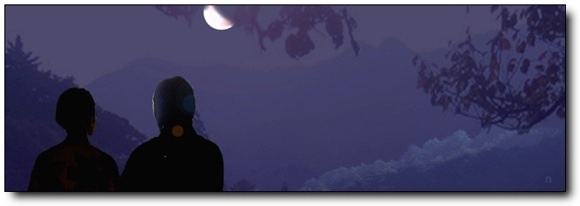
浅い夢の海をうつらうつら漂っているようだった。
腕の中に何か大きくて、熱くて、ぐにゃぐにゃした質量のものを抱えていて、
それが色々に形を変え、ぱちんと弾けると、右の腕にしびれるような感触が残った。
はっとして目を醒ますと部屋はまだ暗かった。
薫はどこかと思わず探ってしまったが、彼女は僕の胸の中にいた。
昨夜、僕が初めて触れたとおりのするするの肌をして、
子猫のように温かく柔らかいまま。
あまりに「しん」、と眠っているので、息をしているのかと心配になり、
そうっと顔のそばに頬を近づけてみると、温かい息がほ、ほ、と僕の顔にかかる。
そのかすかな羽ばたきのような感触が愛しくて、もう一度腕の中にすっぽりと抱き直し、
頬をすり寄せた。
「う・・・ん」
かすかに身じろぎをして、薫が薄目を開ける。
「しょう・・ご」
「ん?」
「よかった。まだ一緒・・・」
僕の頬からあごにすうっと手をすべらせて、ふんわり笑う。
「薫」
「ん」
「薫・・・」
答えが聞こえる前に唇をふさぎ、手を伸ばしてちょっと乱暴に抱きしめる。
「ん・・んん」
薫のくぐもった温かい息が、僕の中に沈んでいた熾き火をまた喚びさましてしまう。
腕に閉じこめて薫の動きをきっぱり封じ、思い切り締めつけて僕の熱を伝える。
薫が苦痛の声を漏らしたが、僕の中の火は消えるどころではない。
月はもう沈んでしまったろうか・・・
貫いた時の薫の声が、さっきより少しだけ甘くなったのを感じながら、
今度こそ、深い眠りの穴に落ちて行った。
体が妙に熱くて、目が醒めた。
外はかなり明るくなり、うす水色の空が見える。
あどけない寝顔の薫が身動きをしたので、こちら向きに胸の中に包み直す。
あれ?
額に手を当てる。
何だか少し熱いような・・・。
腋の下に手を入れると、確かにかなり熱い。
「薫、どうした・・・?」
上半身を起こして声をかけると、濃く生えそろったまつ毛を開いて、
うるんだような瞳を見せた。
「あ、省吾。おはよう・・・」
「薫、調子悪くないか?体が熱いぞ・・」
「う~ん、熱いのかな、わからない。
すごく喉が渇いたの。お水が飲みたい・・・」
「取ってきてやる」
部屋の冷蔵庫からミネラルウォーターを取って戻ると、
薫の顔色がほんのり赤く上気している。
背中に手を入れて、布団の上に起こしてやろうとすると、
体を起こす時にくらっと頭が揺れて、肩をすべった長い髪が枕を掠めた。
「大丈夫か・・・」
「うん」
僕にもたれながら体を起こして、ペットボトルの水を飲み、
ふたをして僕に渡すと、また、布団にくずおれてしまった。
時計は6時15分を回ったところだ。
朝食が7時半からと言っていたな・・・
6時半になるのを待って、フロントに電話をかけ、
連れの具合が悪くなったので、体温計と解熱剤を持ってきてくれるように頼み、
朝食は部屋で取りたいと告げた。
や、まだこんな格好だ!
そこらにくしゃくしゃになっていた浴衣を引っ掛けて、慌てて帯を締め直し、
薫を起こして着せてやると、帯を結んでからまた布団に寝かせた。
え~と、下着がどこかにある筈なんだけど・・・。
すっかり明るくなった部屋で掛け布団を上げ、探し物を見つけると同時に
それとなくシーツをチェックしたが、それらしい痕跡は残っていなかった。
あれ、どういう事だろう。
ま、いいか、今はそれどころじゃない。
薫はぐったりと横になったまま、目を閉じていた。
7時を少し回った頃、ほとほととノックの音が聞こえ、
昨日の仲居さんが、体温計に市販の解熱剤、氷枕を抱えてそっと部屋に入ってきた。
「お連れさまのお具合は如何ですか?」
「昨夜は元気で夕食も全部頂いたんですが、今朝になって体が熱いみたいで・・・」
「そうですか・・・それは心配ですね。」
朝食も後ほどここへ運ばせて頂きますから・・・と言って、廊下の方に合図すると、
男衆が入って来て、薫の寝ていない方の布団を小部屋に運び、
あっと言う間に片付けてしまった。
「チェックアウトは11時ですが、2時頃までなら融通を利かせますから・・・」
お大事に、と言いおいて出て行った。
熱を計ってみると38度2分。熱いわけだ。
薫の頭の下に氷枕を差し込んでやる。
暫くすると、また戸が開いて、朝食が運ばれてきた。
昨夜の夕食と同じように、季節の香りに彩られた膳だったが、
薫の分は土鍋にはいった白粥と、梅干しや漬け物、吸い物などに代わり、
宿の心遣いを感じた。
「薫、辛いかもしれないけど、起きて少し食べないと薬が服めないよ。
温かいうちに頂いた方がいい」
薫を抱き起こして羽織を肩にかける。
手を貸して立たせようとすると、薫が僕の腕をきゅっとつかんだ。
「省吾、ごめんね・・・」
さっきよりもっと赤い顔をして、思い詰めたような表情で見つめている。
「大丈夫だ。これを食べたら少し元気が出るよ。」
薫を座らせて、お粥をよそってやり、僕も自分の朝食を頂くことにした。
浴衣の肩に髪を流し、ばら色の頬をしている薫は
しおらしくて、なんだか妙に色っぽく見える。
ずいぶん、負担をかけてしまったのかな・・・
反省している身としては、余計な発想は押し込めて、おとなしく朝食に集中する。
薫は茶碗に一杯のお粥を食べて、おつゆを少し含み、
持ってきてもらった解熱剤を服んで布団に戻った。
布団の中から僕がお茶を飲んでいるのを、じっと見ている。
小さな子どものような顔つきだ。
「省吾・・・」
「ん」
「一緒にここにいて・・・」
「いるじゃないか」
「ちがう。一緒に隣にいて・・・」
「わかった。先に着替えるよ。」
「いや、わたしだけ浴衣のままなんていや。省吾もそのままでいて。」
「わかった・・・」
そう返事をしたが、朝食を片付けに来るだろう。
僕と薫の膳を玄関に通じる小部屋にまで運び、居間との境の襖を閉めた。
そうして、薫の横の布団に滑り込むと、薫がふっと胸に寄り添ってきた。
熱い頬・・・
僕の胸に直に伝わる薫の熱を感じながら、片方の腕で細い体を抱きしめ、
もう一方のてのひらで、薫の髪や背中をゆっくりゆっくり何度も撫でてやる。
やがて薫のまぶたがふっと閉じられ、まつ毛の濃い影が頬に落ち、
かすかな寝息が聞こえてきた。
そっと体を離そうとすると、薫が察知してすぐに体を寄せてくるので、
ずっとそのままにいるうちに、僕もつい、うとうとと眠ってしまった。
目が覚めると、10時前だった。
薫の体を探ってみると、首の後ろから背中あたりにびっしょりと汗をかき、
鼻のまわりや額にも小さく汗が浮いている。
汗が出たんなら、熱が下がったのかな・・・
額に手を当てると、もうそれほど熱くない。
濡れた浴衣を着替えさせないといけないだろう。
薫はぐっすり眠っているようだが、タオルで顔と首回りを拭ってやり、
布団を半分跳ね上げて、構わず帯をほどくと、
湿った浴衣を開いて肩から抜こうとした。
「きゃ・・・」
薫が気づいて、声を上げ、浴衣の前を閉じようとする。
急に肌が冷えて、目を覚ましたのかもしれない。
「誤解するなよ。汗で浴衣がびしょびしょだから、脱がせるだけだ。
頼むから、おとなしく肩から浴衣を抜いてくれ・・」
その言葉を聞くと、抗うのを止め、おとなしく浴衣を剥ぎ取られるままになった。
剥ぎとった下には何も身につけておらず、布団をすぐに掛けたものの、
朝の光の中に曲線でうねる肌の白さが僕の目に残った。
脱がせた浴衣をざっと畳んで、帯でくるくるまとめておく。
「省吾・・・ここにいて。」
「替えの浴衣いる?」
「ううん、もう要らない。ここにいて、ぴったり側にいて」
温かい布団の中のすべらかな肌にふれると、また僕の中に勃々と湧き起こるものがあるが、
今そんなことをするわけにいかない。
薫は満足そうに、僕の胸にぴったりくっついてじっとしている。
いい気なもんだな、人の気も知らないで・・・。
こういうのって結構辛いんだぞ。
しばらくそのままでいたが、
「薫、これはダメだ。じっとしていられなくなってくる・・・」
仕返しの意味も込めて、ふくらみの先の淡い紅色だけそっと口に含む。
「う・・・」
薫がうめき声をあげ、腕の中で体をくねらせた。
やっぱり、これはまずい・・・。
「薫、今は止めておく。本当に帰れなくなったら困るから、ね?」
今度こそ僕だけ先に着替えると、フロントに電話をし、
仲居さんに玄関の隣の小部屋へ来てもらって清算を済ませた。
「お連れさまはいかがですか?」
「おかげで熱も下がりました。昼には出られそうです。
帰りは駅までタクシーを呼んでもらおうと思っています。」
「かしこまりました。やれ、ひと安心ですね。」
仲居さんが下がってから部屋に戻ると、薫が布団の中からじっとこっちを見ていた。
「気分どう?」
薫は横になったまま、静かに笑って
「うん、もう寒気もしないし、頭もぼうっとしない。
ごめんね。心配かけて・・・」
布団から出て着替えるから、あっちに行け、という。
今さら何だよ、浴衣まで着替えさせたのはこっちだぞ、
と思ったが、黙って縁台の方へ行った。
今朝の渓谷は、陽射しのせいか、昨日よりずっと緑が鮮やかで、
昨夜一晩でさらに黄色や赤の彩りが増えたような気がする。
植え込みの萩の花を指の先にこぼれさせ、冷たい露の感触を確かめていると、
着替え終わった薫がそっと隣に立った。
「少しは元気になったか?」
「うん、色々ありがとう。すっかり省吾に甘えちゃったね」
「いや、たぶん僕のせいだよ。
どこかで薫に無理をさせてしまった・・・ごめんな」
「そんなことないよ。省吾にいろんな風に包んでもらえて嬉しかったの。
省吾がすごく優しくて、あったかい人だってわかったし・・・。
こんなに嬉しかったことってないよ。
きっとずうっと忘れないと思う。」
「なんだ、これで初めてわかったのかよ。
ずっと前から優しいんだよ、わかってなかったなあ・・・薫は」
「うん、わかってなかった。
ここへ来たがるのも、そういう目的だろうって少し疑ってた」
う、全く違うとまでは否定できないな・・・。
「薫と一緒に月が見たかったんだ」
「うん、わたしもね、省吾とずうっと一緒にいたかったの。
ねえ、○ッチのバッグなんかの何十倍も何百倍も、ずうっと素敵な時間を過ごせたよ。
ほんとにありがとうね」
薫がひっそりと胸の中に入ってくる。
抱きしめずにはいられない。
柔らかくて甘い唇に口づけながら、頭の中をほんのかすかな疑問が掠めた。
でも何の痕跡も残らなかったのは何故なんだろう・・・。
初めて・・・だよね?
「どうしたの?」
女の勘は鋭い。
「何か別のことを考えていたみたい・・・」
「何でもないよ。帰りの新幹線の時間をつい考えちゃったんだ」
「早く帰りたいのね。こんな時にひどいわ。」
「そうじゃないよ。薫が心配だからだよ・・・」
他愛ない会話を交わしながら、またぐっと薫との距離が縮まったのを感じた。
これで名実ともに本物の恋人同士になれたかなあ。
あの店の30万ヒットに心から感謝しなくては・・・・。
<終わり>
